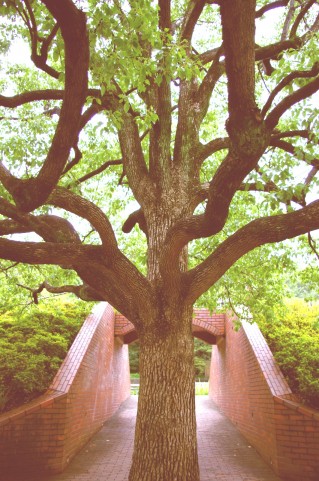矢印は物事の関係性を表す上で、とても便利。
・物事の流れ、
・論理の流れ、
・影響をあたえるものと受けるもの、
といろいろに使える。
いろいろに使えるということは、
矢印は抽象的で、具体的な意味がなくても使えるということだ。
矢印は、線とは違い向きがある、ということ以外は明示してくれない。
すくなくとも、矢印を書く側が、どういう意味をこめて書いているのかは意識するべき。
できれば、違う意味を持つ矢印は、別種の矢印を使うようにしたいものだ。
例: 矢印はそれぞれ向きのあるコネクション、以上の意味があることが多い。
卵買う→掃除→料金支払い
は時間を追って、手順を表しているし、
鎌倉幕府→p.124
は鎌倉幕府のことについて知りたければ、124頁を参照するというアクションを起こせといっている。
弁当持参←購買で買う人は必要ありません
この矢印は補足説明の向きを示しているだけで、括弧で代用した方がいい。
#ただ単に、話の流れ を示しているだけのものもある。
今挙げた例は矢印としては間違いはなく、意味は様々だったというだけだ。
描いた矢印が、因果関係なのか、論理で何かを導いたのか、手順を示しているのか、
そういう区別をしっかりしないと、図の意味がぼやける。
#矢印で描くべきでないところにまで矢印を描くなんてのは論外。