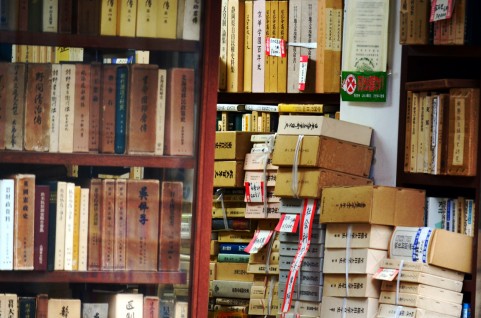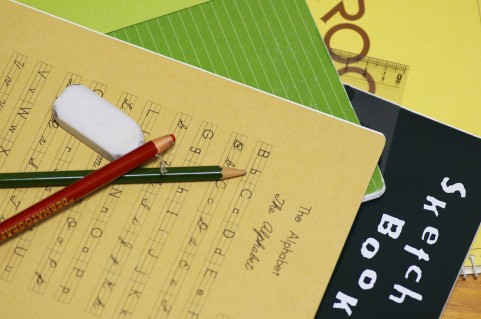永久不変のものは存在しない。だからそれを求めるのは苦しみの元になる。
しかし、ある程度、一貫・継続した行動がとれなければ、行動は効率的ではなくなる。
外部の変化の事実を受け入れ内面を変化させつつも、
時に内面の変化を抑制し一貫した行動を取り、
外部環境を変えていかなければならない。
不変・変化のコントロールは、セルフコントロールの一つの鍵となる。
ものごとは変化してゆくが、人は変わらないことを望む
変化が怖い、変わるのが怖いというのは基本的な悩み。
人間は不変であることを望む。
しかし、変化は起こる。というよりはこの世は変化するもの。
この世の間違いのない法則の一つとして、この世は変化する
と捉えていたほうがいい。
不変を望むことは、以下のような形で現れる:
- 習慣や仕組みの変化を面倒くさがある
- 愛情・別離・生死を受け入れない
- ものごとに執着する
一方で、人は移ろいやすい感情に振り回される
人間の行動はある程度一貫したものとなって始めて
継続による力を得る。
一貫した行動のもとになるものは、
固定された行動の原理、ものの見方である。
しっかりとした状況の把握、方針の作成が一貫した行動を支える。
対して、この行動の原理として、
自他の感情などの揺らぎやすいものを置く場合、
行動から一貫性が失われてしまうことになる。
変化・不変のバランスをとるわけだが
現実は常に変化し続ける。
そして行動のためにはある程度固定した見方が必要になる。
真実と効率性のトレードオフをすれば良いだけの話。
効率性を求めて固定した方法を破棄できないのは問題があるし、
この世の中の変化に刻一刻と引きずり回されるのも問題がある。
変わらないものもあるが、変わるもので有益のものもある
そんななかでも、不易のものがある。変化しないものという意味だ。
知識の中には10年、100年、1000年と通じるものがある。
これは、真実と効率性のトレードオフをしなくても済む有難いものである。
かといって、不易のものばかりを追い求めるのにも問題がある。
ある一時期だけ通用する具体的な知識にも、強力なものはいくらでもある。
この辺りのバランス感覚もまた必要だ。