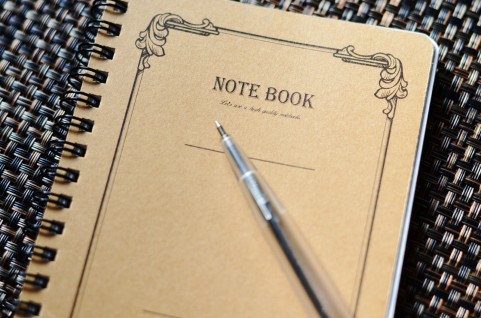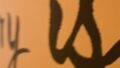人間の理性や知識を超えた難しさを体験
難しさの階層
解説
この文章は「難しさ」に階層があるというテーマを中心に、人間の認識や理解の限界について考察しています。以下に、主要なポイントを解説し、その背景を補足します。
1. 難しさの階層構造
- ポイント:
「規則・礼儀・道徳」から始まり、「利益・価値」を経て、さらにその上に「XXXXX」が位置付けられています。「XXXXX」とは、人間の知識や言語、理論では完全に捉えられないものを指しています。 - 構造:
- 規則・礼儀・道徳:
社会生活の基盤であり、学習や経験を通じて比較的容易に理解できる。 - 利益・価値:
個人や集団の選好や目的に基づく抽象的な概念で、状況や文化によって変動するが目的から理解できる。 - XXXXX:
人間の知識体系を超えたもの。例えば、数理的に記述不可能な事象や、名前をつけられない現象。
- 規則・礼儀・道徳:
- 解釈:
難しさの階層が示すのは、現実に存在する複雑性や未知性の広がりです。下層ほど日常的であり、上層ほど抽象的で非日常的なものに近づきます。特に「XXXXX」は、人間の理性や感覚を超えたものとして描かれています。
2. 「XXXXX」に含まれるもの
- 特徴:
「XXXXX」とは、以下の性質を持つものとして説明されています:- 世俗的な価値から離れたもの:
人間社会のルールや利益に縛られない。 - 記述しきれないもの:
有限の文字の列で書き表すことができない。分類しようとしても有限にならない。 - 名前がつけられないもの:
言語や概念で表現するのが不可能な領域。対象の範囲を限ることもできない。まとめて一つの対象として捉えることすらできない。 - 知識の体系化を超えるもの:
現実のいくつかのあるポイントとなる部分を捕まえて、それらの関係で現実を捉えるというようなことがそもそもできない。
- 世俗的な価値から離れたもの:
- 例:
数学的には、ランダム性や計算論の議論が「XXXXX」に関連しています。
無限集合や超越数(例えば、円周率や自然対数の底 e のような数)などが人間の直感を超える例として挙げられますがこんなものは数式で表すことができるので大したことがありません。
3. 数学における「記述しきれないもの」
- 計算論とランダムネス:
数学では、「計算可能性」や「ランダム性」を通じて、「人間が記述できないもの」の性質が研究されています。擬似乱数は有限の規則から生成されるため、本質的には規則性を含んでいますが、真のランダム性とは異なります。圧縮不能な数字の列という定義を取るならば、こんな乱数列は人間に書き表すことはできません。定義そのままやがな。 - 実数と自然数の濃度:
数学的な視点から「理解できないもの」の広がりを説明するために、以下の関係が述べられています:- 全ての実数 > 全ての自然数:
実数の集合は非可算無限であり、自然数の集合(可算無限)よりもはるかに大きい。
永久に書き続けることができたとしても終わりません。抜けまくります。 - 全てのプログラム:
有限の規則で記述できるものの範囲は、自然数の集合に対応する。つまり、無限の実数の中で記述可能なものはほんの一部に過ぎません。無限の時間が合っても無駄です。
- 全ての実数 > 全ての自然数:
- 補足:
「記述しきれないもの」は、数学的には確率や無限の概念と結びつきます。これを日常に落とし込むと、認識や行動の限界を示唆するものと捉えられます。
4. 人間の行動と価値観の制約
- ポイント:
人間が価値観を定め、それに基づいて行動することの限界が指摘されています。「価値観を持つこと」や「行動を選ぶこと」は、現実的には困難が伴うものの、難しさの階層全体から見るとそれほど重要ではないとされています。 - 理由:
- 狭い範囲の理解:
人間の価値観や行動は、ほとんどが有限の規則や記述可能な枠内に収まる。 - 技術の限界:
広い意味での技術(科学、哲学、実践)は非常に面白いものの、未知の全体像に比べると小規模なものでしかない。
- 狭い範囲の理解:
5. 理解できないものへの態度
- ポイント:
最後に、人々が「自分の理解を超えたものが存在する」という前提で行動できていないことが強調されています。 - 解釈:
多くの人は、自分の知識や経験の範囲内で世界を解釈しがちです。その結果、「XXXXX」に代表される未知や無限の存在を認識せず、行動や思考を制限してしまいます。 - 教訓:
人間が理解しきれないものを前提として受け入れることで、謙虚さを持ち、より深い洞察や探求の可能性が広がります。
補足説明
難しさの階層と哲学的背景
- カントの「物自体」:
人間が認識できる現象は、知覚や理性を通じたものに限られ、それを超えた「物自体」は直接的には捉えられないとされています。「XXXXX」に相当する領域は、この「物自体」に類似しています。 - ハイデガーの存在論:
「存在そのもの」は、言語や概念で完全に表現することができず、人間の認識を超えた領域にあるという考え方と関連しています。 - 存在そのものまで行かなくても
「もっとも重要なのは、事実的なもののすべてがすでに理論であると悟ることだ。現象の背後に何も求めてはならない。現象そのものが理論なのである。」 ゲーテさん
「言えば言うほどそれる」という趣旨の言葉は、老荘思想の文脈でよく取り上げられるテーマですが、具体的にこれに該当する表現は『老子』や『荘子』の中に直接は登場しません。ただし、このような概念を含む似たような表現はいくつか見られます。
例えば、『老子』第56章には次のような一節があります
「知る者は言わず、言う者は知らず。」
(知っている者は語らず、語る者は知らない。)
これは、真理や道(タオ)は言葉で説明することができず、言葉にすればするほど本質から外れてしまうことを示唆しています。この一節は、「言えば言うほどそれる」という考え方に近いと言えます。
また、『荘子』にも以下のような思想が反映された箇所があります:
「道は言うこと能わず。」
(道は言葉で語ることはできない。)
『荘子』の中では特に「言葉の限界」について言及し、道や真理は言語では捉えられないという哲学的立場が繰り返し強調されています。
このように、老荘思想では、言葉による説明が本質を損ねるという考え方が根底にあり、「言えば言うほどそれる」という現代の表現にも通じる要素が見受けられます。
人間の記述能力なんてこんなものだということが昔から知られているのだな。
なんでも知ってるとか言っている原始人はなんとかしろよ全く。カーチス・ルメイに石器時代に戻してもらえよお前が住んでる所。
2. 数学と哲学の交点
- 数学では、無限や非可算性を扱うことで、「記述できないもの」の一端に触れています。
- 哲学では、これを抽象化し、人間の認識や行動がどこまで広がり得るかを問います。
3. 日常生活への応用
- 自分の理解を超えたものがあることを受け入れることで、思考の柔軟性が高まります。
- 価値観を定める際には、その背後に隠れた未知の要素を意識することで、より包括的な判断が可能になります。
- 人間がワーワーわめいてる偉そうなことでは現実を捉えることは全然サッパリできないということがわかれば、思い上がった人間の言う事や世間で言われていることを本気にする気がなくなります。あほくさ。
結論
この文章は、難しさの階層を通じて、人間の理解や行動が抱える限界と、その背後に広がる未知の重要性を示しています。「XXXXX」に象徴されるものは、人間の理性や知識を超えた存在として、謙虚に受け入れるべき対象です。この視点は、個人の成長や科学的探求、倫理的判断において重要な指針となります。