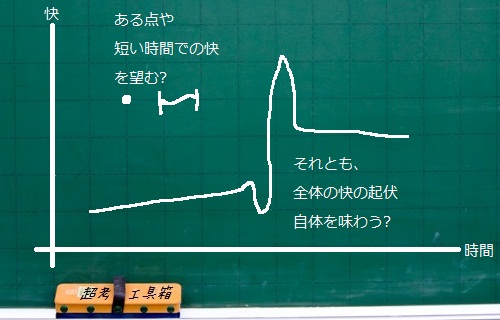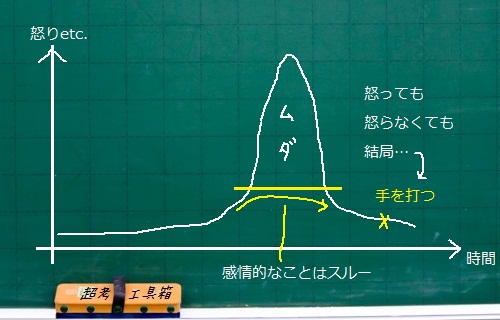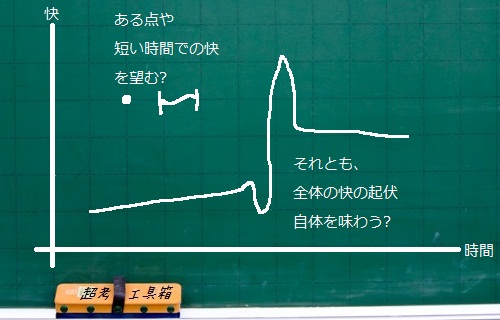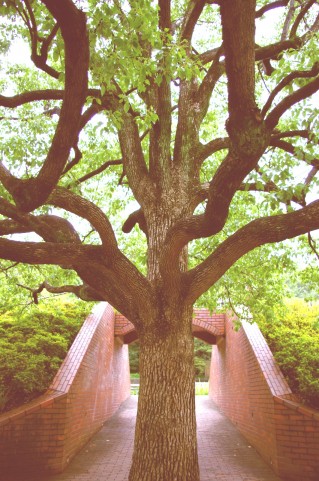いつぞや、先輩と妻と3人で呑んでいて、
妻: 何でそんなにしんどいコトしてるの?? 楽に生きたらいいのに
と聞かれた。私と先輩の答えは、
一度、カタルシスを覚えた人間は、楽しい、に戻れない
だった。
でもこんなのは実は序の口だった。
幸せはある点での概念。
幸せを求める、という言葉の使われ方を見ていると、
変化を捉えているものとは思えない。
時間の各点、各点で捉えるためのバラメータとして扱われているようだ。
変化は辛いこと?
変化することは、時として良くないことともされる。
安定、順調などという言葉の使われ方をみても、それは感じ取れるだろう。
変化を受け入れるという言い方からも、自然に受け入れるものとは言いがたいものの場合もある。
ある一定の幸福を維持しようとするは、不変のものが少ないこの世の中では、無理な話。
安定・固定した幸福を求めるのは、辛さの元。
変化を上手く受け入れればいいわけだ。
マイナスや下げ調子をどうすればよいだろう?
変化をひと塊として、安定して捉える
冒頭では、カタルシスの話が少ししていだけども、幸福、快、などにはいろんな波の形がある。
実は、各パターンで結構楽しみ方・味わい方がある。
固定した何かではなく、その変化自体に喜びを見出してしまえばいい。
待ちわびる、なんてのはその典型。
待たされるというと悪いことのようだけれども、状況が許せば、
楽しいことを事前に感じ続けること、という悪くない形でもある。
カタルシスのパターンは、待ちわびる+いつ来るか分からない大波、というもの。
ある意味、博打的楽しみがある。
注意: パターンには揺れがある
このパターンもバリエーションがあって、何年も待ちわびるものもある。偽物の山場が何度も来るものもある。
固定したパターンが出現するわけでもないので、その当たりの揺れもひっくるめて俯瞰的に見ないとつまらない。
注意: 実生活での変化のスパンは長い
ドラマなどのストーリーや、音楽のジャンルを見ていると、それぞれに特有のパターンを見つけることができることがある。二時間ドラマでも、ブルースでも、ラブストーリーでも、この手のパターンが練り込まれている。
ただ、実生活では長いスパンでパターンが現れるので、把握しづらい。少し引いて見ると分かりやすいかも知れない。
さらに: 変化を飲み込む、すべてを飲み込む楽しさ
変化をひと塊として見ることができるようになり、
変化のバリエーションも一つのものとして分かるようになり、
変化のパターンの大きな分類にも慣れ親しむと、
次には不思議な段階がやってくる。
次はどんな形がやってくるのか、という期待が湧いてくる。
さらには、
感じるすべてを、ひたすらに受け入れて飲み込んでいく、何もかもが味わい深くなる瞬間
がやってくる。至福の時が来る。
(そのことを予感させていた本がある↓)
じゃあ、何が起こっても良いのか、幸せでなくても良いのか?
そのまえに、
幸福とは何か?
よくある幸せの捉え方は、到達点だったり、維持するものだったりと、対象として、ある種のゴールとしてというのが一般的かと思う。
燃料としての幸福
でも、「生きていくための燃料」として捉えることもできる。無くては非常に生きづらい。
「幸せ断ち」を実験的にやってみたが、酷い結果だった。何度もやってみたけど酷い有様だった。
さらには、幸せはそれがあったとしても、それで十分なわけでもない。
ある程度は常にあった方が、スムーズに生活を送れるものである、というのは間違いがなさそうだ。
(そんなことを考えているときに、MITだかカーネギーメロン大学だかで同じようなことを書いてある文章を見た…はずなんだけれどもリンクも、それを発見するためのキーワードも失ってしまった…無念。)
そんなわけで、幸福は到達点ではなくて、燃料として備えておくものじゃないだろうか。
長いスパンでの人生の味わいなども、ある程度の幸福を必要とするかも知れない。ランニングコストとして。